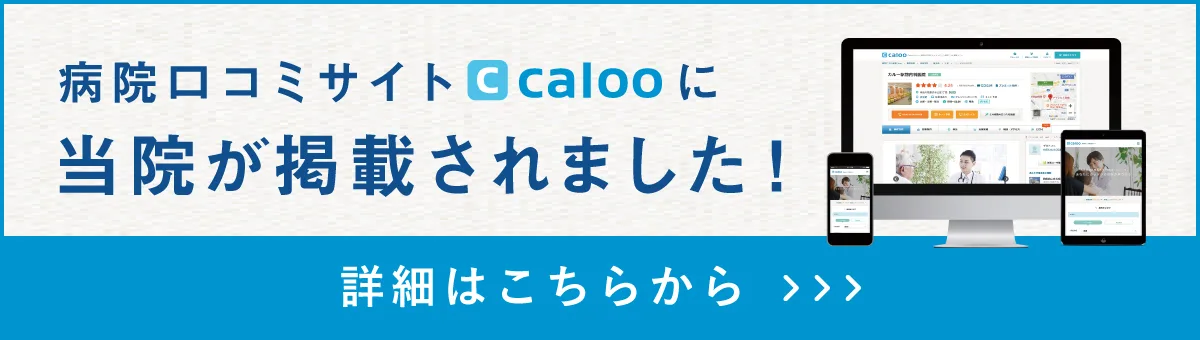食欲がないとは
食欲がない、つまり食欲低下とは、通常の食事をとりたいという気持ちがなくなる状態を指します。
特に思い当たる原因がなくても、しばらくの間食欲が落ちることもありますが、長期にわたる場合や体重減少などの症状が伴う場合は、身体や精神に何らかの問題が生じている可能性があります。

食欲がなくなる原因
- 消化器疾患:胃炎や胃潰瘍、胃食道逆流症(GERD)など、消化器官に不調があると、胃がムカムカする、胃もたれがあるなどの症状が出やすくなり、食欲が低下します。
- 感染症:風邪やインフルエンザ、胃腸炎などの感染症も一時的な食欲低下を引き起こします。発熱や倦怠感を伴うことが多く、感染が治まると食欲も回復することが一般的です。
- 甲状腺機能の異常:一部の薬(抗生物質、抗うつ薬、化学療法薬など)は、食欲を低下させる副作用があります。特に長期にわたって服用する薬や、強い薬では影響が大きくなることがあります。
- ストレスや精神的な問題:精神的なストレスや不安、うつ病は、食欲に直接的な影響を与えることがあります。強いストレスを感じているときや、心身が疲れているときは、食事が喉を通らなくなることが多いです。
- 高齢による食欲の低下:加齢に伴って味覚や嗅覚が鈍くなり、食欲が低下することが一般的です。また、消化機能の低下も影響し、特に高齢者においては注意が必要です。
食欲がない時に考えられる病気
- 胃炎や胃潰瘍:胃の粘膜が傷つくことで、胃の痛みや不快感が生じ、食事をとることが苦痛になるため、食欲が低下することがあります。
- 肝臓や膵臓の疾患:肝臓や膵臓の機能が低下すると、消化不良や食欲低下が起こりやすくなります。特に肝炎や膵炎、肝硬変などでは食欲不振が代表的な症状のひとつです。
- 心不全や腎不全:重度の心不全や腎不全は、全身のエネルギー代謝に影響を及ぼし、食欲が減少することがあります。むくみや倦怠感、息切れなどの症状も併発することが多いため、総合的な検査が必要です。
- がん:一部のがんは、進行するにつれて食欲を減少させることがあります。消化器系がんや肺がん、膵臓がんなどでは、早期に食欲不振が現れることが多く、体重減少も併発するため注意が必要です。
食欲がない時の対策
- 少量でも栄養価の高い食事を摂る:食欲がないときでも、少量で栄養が補えるように工夫することが大切です。豆腐やスープ、ヨーグルト、果物など、消化が良く栄養価が高いものを少しずつ摂取しましょう。
- 食べやすい形状にする:固形物が食べづらいと感じる場合は、スムージーやポタージュスープなどにして、飲みやすくするのも一つの方法です。
- ストレス解消を心がける:精神的なストレスが原因である場合は、リラクゼーション法や趣味の時間を取り入れて、ストレス解消を図ることが有効です。睡眠をしっかりとり、生活リズムを整えることも食欲改善につながります。
- 食事時間を定める:一日の中で規則正しい食事時間を決め、食欲がなくても少しずつ摂ることで、体がそのリズムに慣れてくることがあります。少しでも食事を摂ることで、食欲が少しずつ戻ることが期待されます。
下記に当てはまる場合、当院までご相談ください
- 体重が急激に減少している:食欲が低下することで体重が急激に減少している場合、体に負担がかかるため、早急な対応が必要です。
- 食欲不振が数週間続いている:数日程度の食欲低下であれば一時的なものとして様子を見ることもできますが、2週間以上続く場合には、原因を特定するために医師に相談しましょう。
- その他の症状が併発している:食欲不振と共に発熱や倦怠感、胃の痛み、むくみなどの症状がある場合、内臓疾患や感染症の可能性が考えられます。