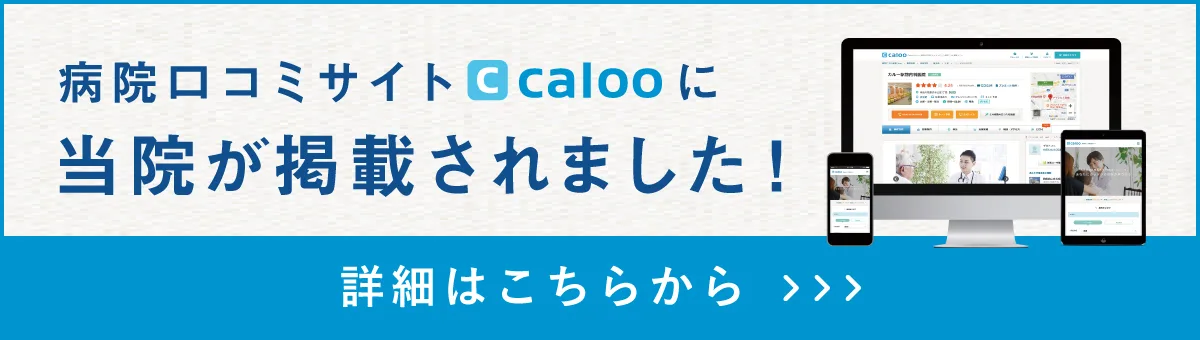食道裂孔ヘルニアとは
食道裂孔ヘルニアは、横隔膜の食道が通る部分(食道裂孔)が緩むことによって、胃が胸腔に飛び出す状態を指します。
通常、横隔膜が腹部と胸部を隔てており、食道裂孔が食道の通り道として機能しますが、さまざまな原因によってこの部分が広がり、胃の一部が胸部に押し上げられることがあります。
食道裂孔ヘルニアは、特に中高年の方に多く見られ、肥満や妊娠、加齢が関係しています。
また、逆流性食道炎を併発しやすい傾向もあるため、注意が必要です。

食道裂孔ヘルニアの原因
- 加齢:年齢とともに横隔膜や筋肉が弱まり、食道裂孔が広がることで、ヘルニアが発生しやすくなります。
- 肥満:体重が増えると腹圧が高まり、食道裂孔が押し広げられ、胃が上にずれやすくなります。
- 妊娠:妊娠中は腹圧が増し、横隔膜にかかる圧力も上がるため、食道裂孔ヘルニアのリスクが高まります。
- 遺伝的要因:遺伝的に食道裂孔が広がりやすい家系も存在し、その場合、若年層でも発症する可能性があります。
- 姿勢や生活習慣:前屈みの姿勢や重い物を持ち上げる動作が多いと、腹部に圧力がかかり、食道裂孔に負荷がかかることがあります。
これらの要因が複合的に作用して、食道裂孔ヘルニアの発症に繋がります。
食道裂孔ヘルニアの症状
- 胸やけ:胃酸が逆流することにより、胸の中央部や喉に焼けるような痛みや不快感が生じます。
- 呑酸(どんさん):酸っぱい胃液が喉まで逆流してくる感覚があり、特に食後や横になったときに強くなる傾向があります。
- 胸の痛み:胸やけとは異なり、圧迫感や痛みが胸部に感じられることがあります。
- 嚥下障害:食べ物が喉を通りにくくなる、または胸の奥でつかえる感じがすることがあります。
- げっぷや腹部膨満感:消化不良が起こりやすく、げっぷやお腹の張りを感じることが増えます。
これらの症状が継続する場合は、放置せずに早めに当院までご相談ください。
食道裂孔ヘルニアの予防
- 健康的な体重を維持する:肥満は腹圧を高めるため、適正体重を保つことが重要です。特に腹部に脂肪がつかないよう、適度な運動とバランスの取れた食事を心がけましょう。
- 食後すぐに横にならない:食後2〜3時間は横になるのを避け、消化を助けるために軽い運動を行うと良いでしょう。
- 食生活の改善:脂肪分や酸味の強い食べ物、炭酸飲料は胃酸を増加させるため、これらの摂取を控えることが大切です。
- 重い物を持ち上げない:腹圧がかかる動作を避け、前屈みの姿勢を取らないようにすることでリスクを減らせます。
- ストレス管理:ストレスは胃酸分泌を活発にし、逆流の原因となることがあります。リラックスした生活を心がけましょう。
生活習慣を整えることで、食道裂孔ヘルニアの予防に役立てることができます。
食道裂孔ヘルニアの治療
- 薬物療法:軽度の症状には、逆流性食道炎を抑えるための薬が使用されます。主に胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーが処方されます。
- 生活習慣の改善:食道裂孔ヘルニアは生活習慣の見直しによって症状が改善することがあります。食後の横になる習慣を控えたり、少量ずつ頻回に食事を取ることで症状を緩和させます。
- 外科的治療:症状が重く、薬物療法や生活習慣の改善で効果がない場合は、手術が検討されます。腹腔鏡手術により、胃を適切な位置に戻し、食道裂孔を縮小する治療が行われます。
多くの場合、薬物療法と生活習慣の改善で十分に症状がコントロールされますが、症状が進行した場合は手術が必要となることもあります。
最近の傾向と今後の動向
日本でも高齢化に伴い、食道裂孔ヘルニアの患者数が増加傾向にあります。
特に逆流性食道炎を併発する例が多く、適切な診断と治療が求められています。
また、腹腔鏡手術の技術が進歩し、より安全で短時間の治療が可能となっているため、重症例でも回復が早くなってきています。
今後は、生活習慣病としての食道裂孔ヘルニアに対する認識が高まり、より早期に症状を改善するための治療や予防方法の研究が進むと考えられます。