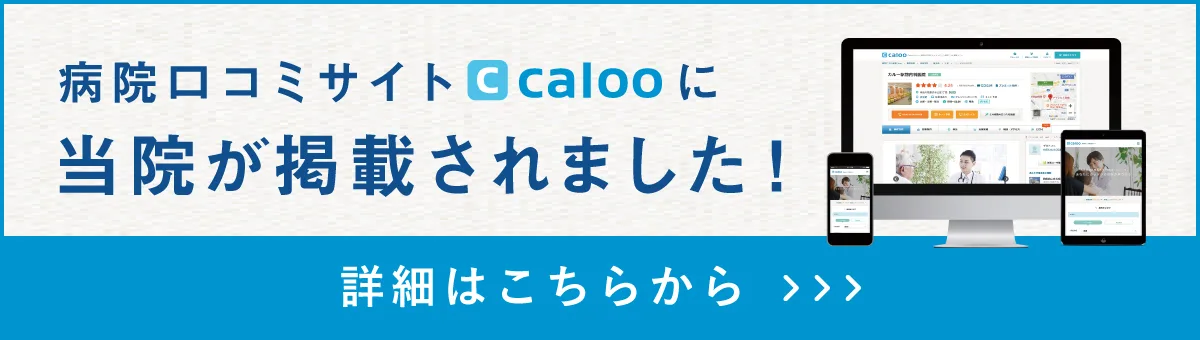大腸憩室症とは
大腸憩室症は、大腸の壁の一部が外側に向かって袋状に突出した「憩室(けいしつ)」が形成される疾患です。
憩室自体は特に珍しいものではなく、高齢者や便秘がちな人に多く見られますが、憩室に炎症が起こると症状が現れ、治療が必要となる場合があります。
この状態を憩室炎と呼びます。
大腸憩室は大腸のどの部分にも形成される可能性がありますが、特に左側結腸(S状結腸)に多いとされています。
一方で、アジア人では右側結腸に憩室ができることも少なくありません。

大腸憩室症の原因
- 加齢:大腸の壁が加齢によって弱くなると、内圧に耐えられなくなり憩室が形成されやすくなります。
- 食生活:食物繊維が不足していると、便秘になりやすく、大腸内の圧力が上昇し憩室ができやすくなります。特に欧米型の食事(高脂肪・低繊維)が影響するとされています。
- 便秘と腸内圧力:便秘により腸内に圧力がかかると、腸壁の弱い部分が外側に押し出され憩室が形成される可能性があります。
- 遺伝的要因:家族歴がある場合、遺伝的に憩室ができやすい傾向があります。
- その他の要因:肥満や運動不足、喫煙も憩室症のリスクを高めると考えられています。
大腸憩室症の症状
- 腹痛:特に左下腹部に痛みを感じることが多いです。
- 発熱:炎症が進行すると発熱を伴う場合があります。
- 便通異常:下痢や便秘が見られることがあります。
- 血便:憩室から出血すると、鮮血便や黒色便が出る場合があります。
- 悪心・嘔吐:炎症が強くなると、消化機能が影響を受けることがあります。
症状が軽度であれば自然に改善する場合もありますが、重症化すると腸閉塞や穿孔(腸壁の穴)などの合併症を引き起こす可能性があるため、早めに当院までご相談ください。
大腸憩室症の予防
- 食物繊維を多く摂取する:野菜、果物、全粒穀物など、食物繊維を豊富に含む食品を積極的に摂りましょう。これにより、便通がスムーズになり、腸内圧力が低下します。
- 水分を十分に摂る:水分摂取は便を柔らかくし、便秘を防ぐのに役立ちます。
- 適度な運動:定期的な運動は腸の動きを活発にし、便秘予防につながります。
- 便秘の改善:便秘が憩室形成のリスクを高めるため、適切な食事と生活習慣で便秘を防ぐことが大切です。
- 禁煙と適切な体重管理:喫煙は腸内環境に悪影響を及ぼし、肥満は腸内圧力を高める可能性があります。
大腸憩室症の治療
- 無症状の場合:症状がない場合は治療は不要で、定期的な観察と生活習慣の改善が推奨されます。
- 軽度の憩室炎の場合:抗生物質を使用し、食事内容を調整して炎症を抑える治療が行われます。多くの場合、外来治療で対応可能です。
- 重度の憩室炎や合併症の場合:入院治療が必要になることがあります。絶食や点滴、場合によっては外科的手術(憩室を含む大腸の一部切除)が行われることがあります。
- 再発予防:憩室炎が再発しやすい場合、食生活や運動習慣の改善を行い、再発リスクを下げることが重要です。
最近の傾向と今後の動向
近年、大腸憩室症の患者数は増加しています。
特に高齢者人口の増加や食生活の変化が影響していると考えられます。
また、内視鏡検査の普及により、無症状の憩室が発見されるケースも増えています。
今後は、より低侵襲な治療法や炎症を早期に抑える新しい薬剤の開発が進むと期待されています。